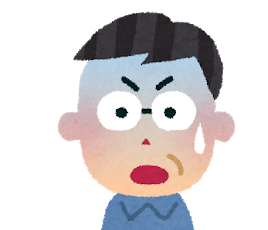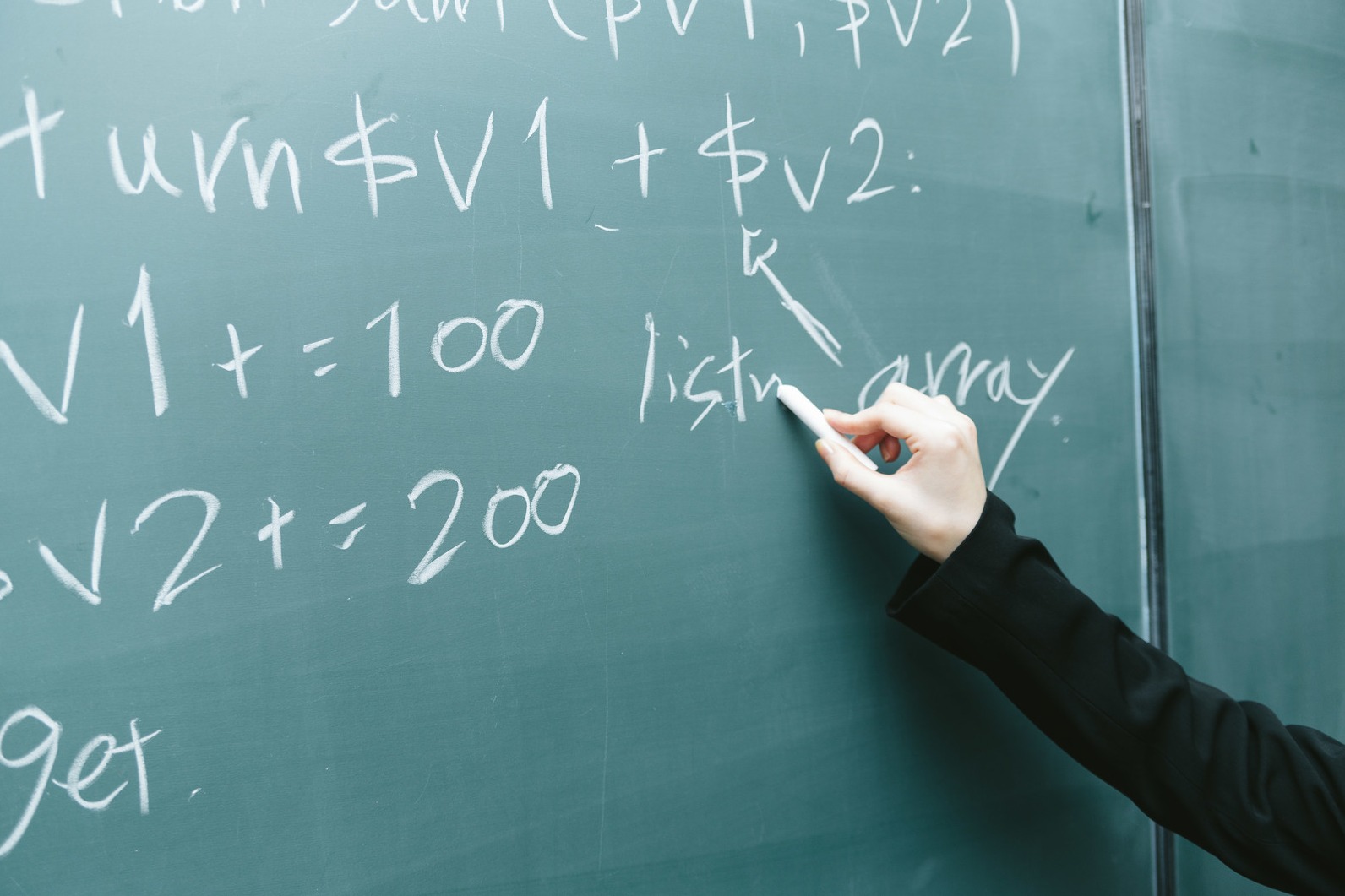こんにちは!
今回は、分析の基本的な考え方についてご紹介します。
分析という言葉はよく聞きますが、
分析ってどうやればいいか、ピンとこないなー
と感じている昔の私のような人は多いと思います。
そんな私もコンサル会社に転職し、壁に当たりながらも「分析ってこんな感じかなぁ」というのがわかってきました。
ぜひご参考にしていただければ幸いです。
分析とは
分析には2つの要素が必要だと私は思っています。
分析の1つ目の要素
1つ目は、これは皆が言っていることですが、分析とは「比較すること」です。
太郎くんの身長は180cmだ!
というのは単なる事実ですが、
男子の平均身長が170cmだ。
一方、太郎くんの身長は180cmだ。
太郎くんは「高身長」だ。
といった感じで、比較すると解釈ができるようになります。
つまり、比較をすることで、事実に意味を持たせることができるようになります。
これが分析の基本です。
分析の2つ目の要素
では、「比較をすること」は全て分析なのでしょうか?
以下の場面を考えてみてください。
あなたは飲み会の幹事です。
参加者は3人で、中華屋に予約の連絡をしたところ、
3人の予約ですね。承りました!
当日は4人テーブルにご案内します。
との回答がありました。
当日、参加者の一人から
太郎が飲み会に参加したいって言ってるんだけど、大丈夫かな?
と連絡があり、あなたは
4人テーブルで予約してるから、1人なら大丈夫だよ!
と返答しました。
この場面でのあなたの「4人テーブルで予約しているから、1人なら大丈夫だよ」という発言は、分析を根拠としたものです。
つまり、あなたは、
- 元々飲み会の参加者は3人
- 飲み屋では4人テーブルを使える
という二つの事実の比較から、「急遽1人が増えても大丈夫」という意味合いを抽出したことになります。
ちなみに、ここでもし
「今回のお店は中華」
だが、
「前回の飲み会は和食」だ!
と比較したらどうでしょうか? 分析と言えるでしょうか?
え?
飲み会の人数の話だったのに、なんでお店が中華か和食かという話になるの?
唐突すぎて意味がわからない…
と思っている人と思いますが、まさにその考えは正しいです。
つまり、「比較したら全て分析になる」ということはなく、「文脈に沿った比較が分析になる」ということになります。
すなわち、「目的」が分析に必要な要素の2つ目です。
上記の飲み会の話を聞くと当たり前に感じると思いますが、仕事においてこの ”目的を無視した比較”をしてしまう人はめちゃめちゃ多いです。
この「目的を考えずに比較をしてしまう」は、若手コンサルのあるあるだと思います。
上司に、
このデータを使った分析お願いね〜
と言われた時に、
分析とは比較だ!
たくさんグラフを作って分析するぞ!
と考え、色々な数字のグラフを作って比較をします。
そして上司に確認してもらった際に、
で?
色々グラフを作ってもらったのはわかったけどさ…
分析結果は、一言で言うと何なの?
…(何も答えられず)
となってしまうパターンです。
私も何回も経験があります。
皆さんは
- この分析の目的はなんなのか?
- 目的に照らした時、どの事実を比較したら”分析”と呼べるのか?
は常に念頭に置くようにしましょう!
分析のパターン
「分析 = 目的に適した比較」と前述しました。
ここでは「比較にはどんなバリエーションがあるか」、つまり、分析のパターンをご紹介します。
分析のパターンは以下の3つと考えるといいと思います。
- (単純な)比較
- 分類
- 予測
厳密にいうと、「分類」も「予測」も比較の一種だと思いますが、作業としてやることがあまりに異なるので、分けて理解した方が実務上いいと思います。
では、この3パターンの詳細をそれぞれ見ていきましょう。
(単純な)比較
グラフで数字を比較したり、定性情報を比較する分析です。
具体例を見ていきましょう。
<数値の比較>
太郎くんの身長が180cmで、平均的な男性の身長は170cmの時、「太郎くんは身長が高い」と言える。
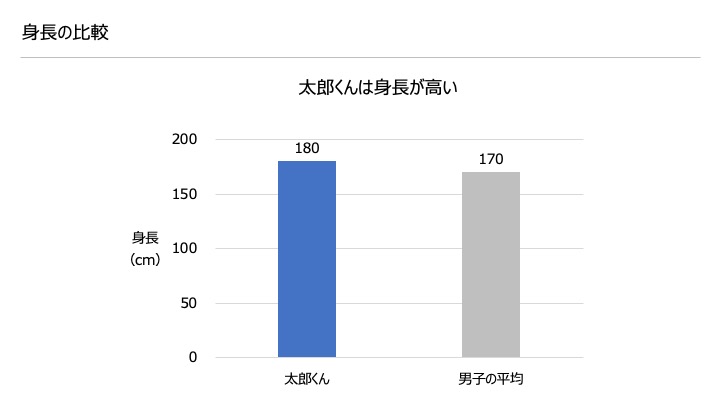
<構成比>
お小遣いの使途のうち、60%がお菓子代。
だから、貯金を阻む最大の障壁は、お菓子代だ。
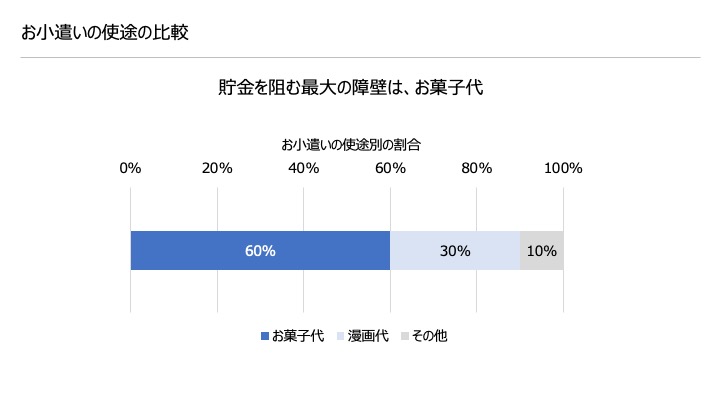
<視覚情報・画像・イラストの比較>
左のサンマは痩せ細っているが、右のサンマは丸々太っている。
だから、同じ値段なら、右のサンマを買うべきだ。

<構成要素の比較>
この部屋はモノトーンなインテリアで統一されているのに、ベッドだけ色が浮いている。
だから、この部屋がオシャレじゃないのは、ベッドのせいだ。

<理由・原因の比較>
失敗しているラーメン屋は、全員が美味しいと感じるラーメンを作ろうとしている。
成功しているラーメン屋は、特定層にだけ支持されればいいと思っている。
ラーメンで成功するためには、ターゲットの絞り込みが必要だ。
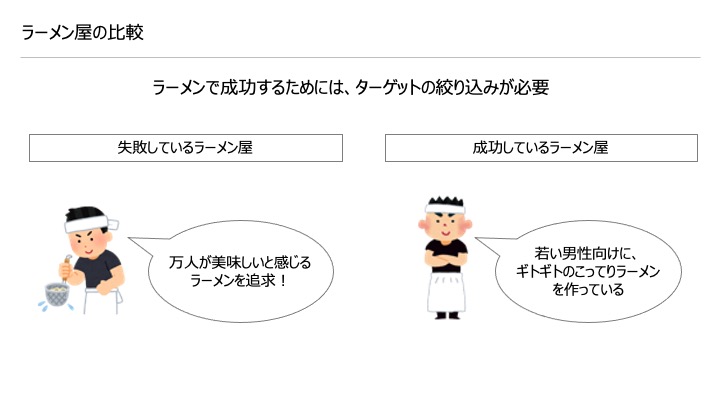
分類
特徴などの差異に基づき、各要素をカテゴリー分けする分析です。
具体例を見ていきましょう。
<グルーピング>
会社で定例会議が乱立している。
会議を目的ごとにグルーピングし、「情報共有の会議」に該当したものは廃止してメールで情報共有するようにする。
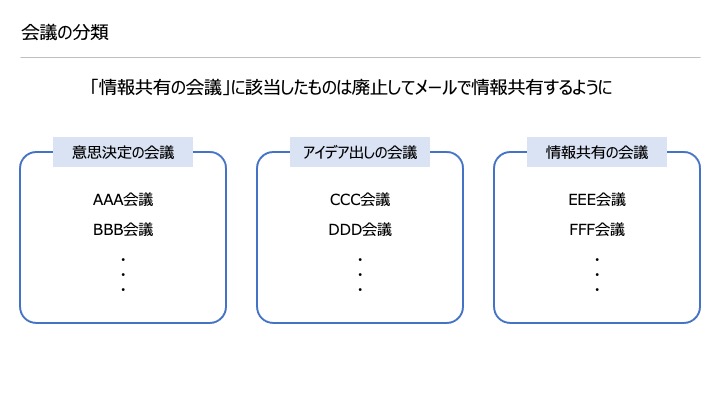
<振り分け・ピックアップ>
アプリで不具合が多発している。
影響を受けているユーザー数が多い10個の不具合にまず対応することとし、ほかは後回しにする。
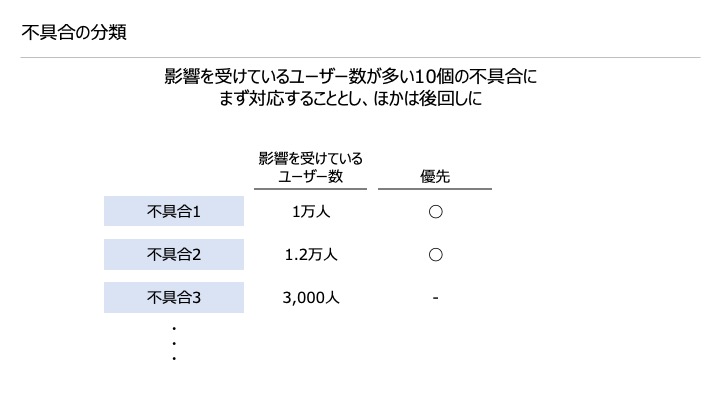
予測
事実や仮定を積み上げて将来をシミュレーションする分析です。
具体例を見ていきましょう。
<定量の予測>
地域の人口は毎年数千人減っていっているし、コーヒー豆も毎年数十円値上がりしている。
だから、あのカフェの3年後の利益額は60%まで落ち込むだろう。
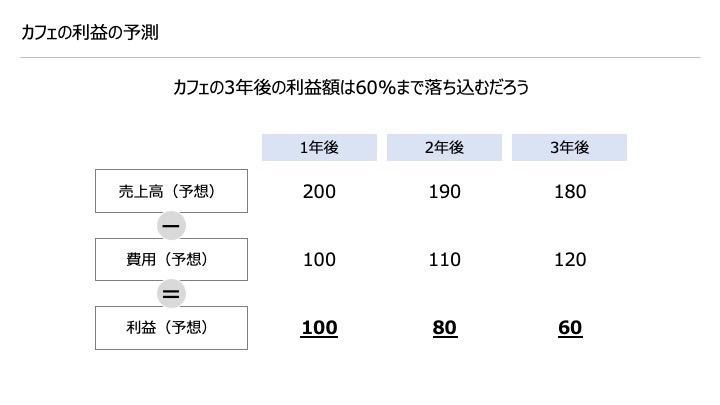
<定性の予測>
ジョブズの自伝にハマった人は起業にチャレンジする傾向がある。
太郎くんは今ジョブズの自伝にハマっているので、将来的に起業にチャレンジするのではないか。

参考:分析に関するほかの記事
この記事の他にも、いくつか分析に関する記事を書いておりますので、そちらも参考にしていただければ嬉しいです!






おわりに
以上です。
いかがでしたでしょうか? 少しでもお仕事などのご参考になれば幸いです。