こんにちは!
今回はフェルミ推定の具体例についてご紹介します。
お題は「年賀状の市場規模は?」です。
今回も、制限時間10分で私が考えた回答を文字起こししていきます。
フェルミ推定については、以前記事を書きましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
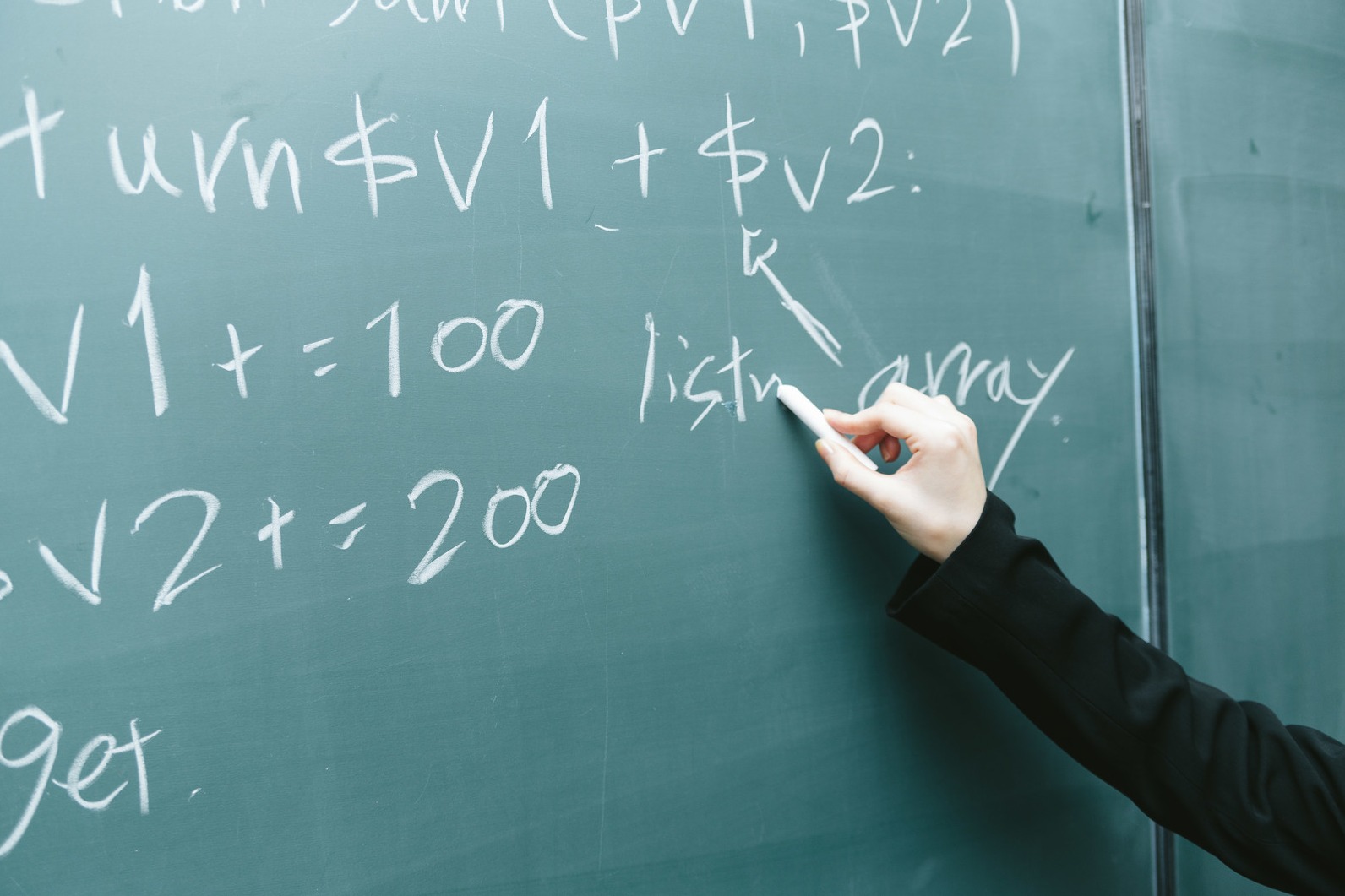
では、早速いきましょう!
イメージを膨らませる
まずは、いつもの通り、「妄想」してイメージを膨らませましょう。
今回のお題は「年賀状の市場規模は?」ですね。
とりあえず、
年賀状と聞いて、思いつくことはどんなことがあるだろう?
と考え、どんどん挙げていくと、
- 年賀状はほとんどもらってないし、送ってもないな
- 公務員時代は結構送ってたなぁ
- お年玉付き年賀はがきとかあるな
- 企業から年賀状が送られてくることもあるな
といったことが思いつきました。
イメージを膨らませるのはこれくらいにして、具体的な検討に入っていきましょう。
最初の立式
では、イメージも膨らませましたし、本格的な検討に入っていきましょう。
特に最初の立式は、複数案出して、比較することが大事です。
A:年賀状の市場規模 = 年間購入枚数 × 年賀はがきの値段@1枚
B:年賀状の市場規模 = 郵便局数 × 販売する年賀状数@1郵便局
そして、
どちらの計算式の方が良いだろう?
と考えましょう。
個人的には、Aのほうが良いと思います。
年賀はがきは最近はコンビニなどにも売っていますので、Bだと漏れがあるでしょう。
なので、以降はAの計算式で検討していきます。
フェルミ推定の計算式については、以前記事を書きましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
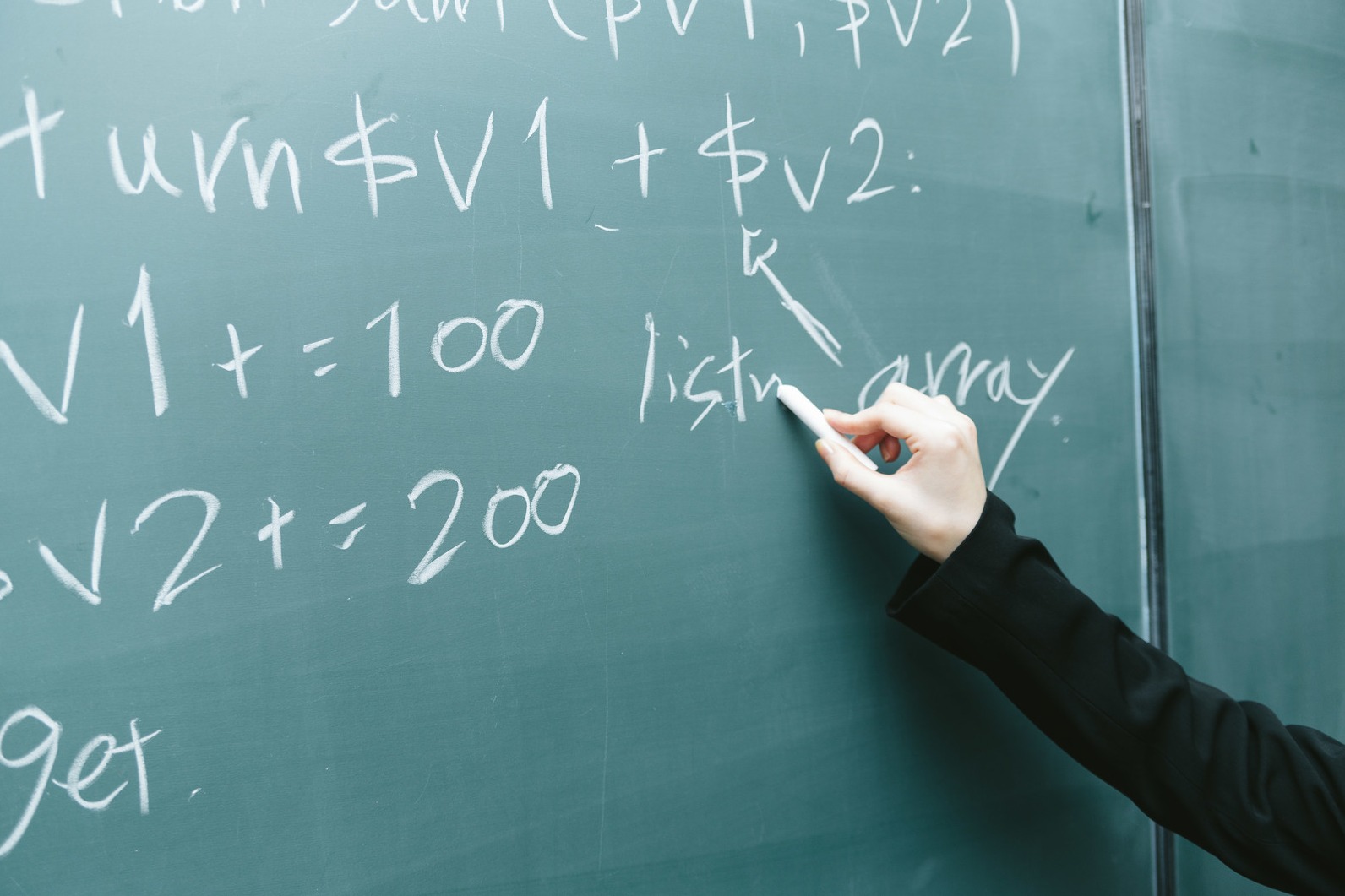
数字を置こう
A:年賀状の市場規模 = 年間購入枚数 × 年賀はがきの値段@1枚
をベースに、
数字を置ける変数はあるかな?
と考えると、「年賀はがきの値段@1枚」は置ける気がします。
だいたい一枚50円くらいでしょう。
なので、「年賀はがきの値段@1枚」は50円と置きましょう。
一方、「年間購入枚数」については、皆目見当がつかないので、さらに分解していきましょう。
フェルミ推定の数字の置き方については、以前記事を書きましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
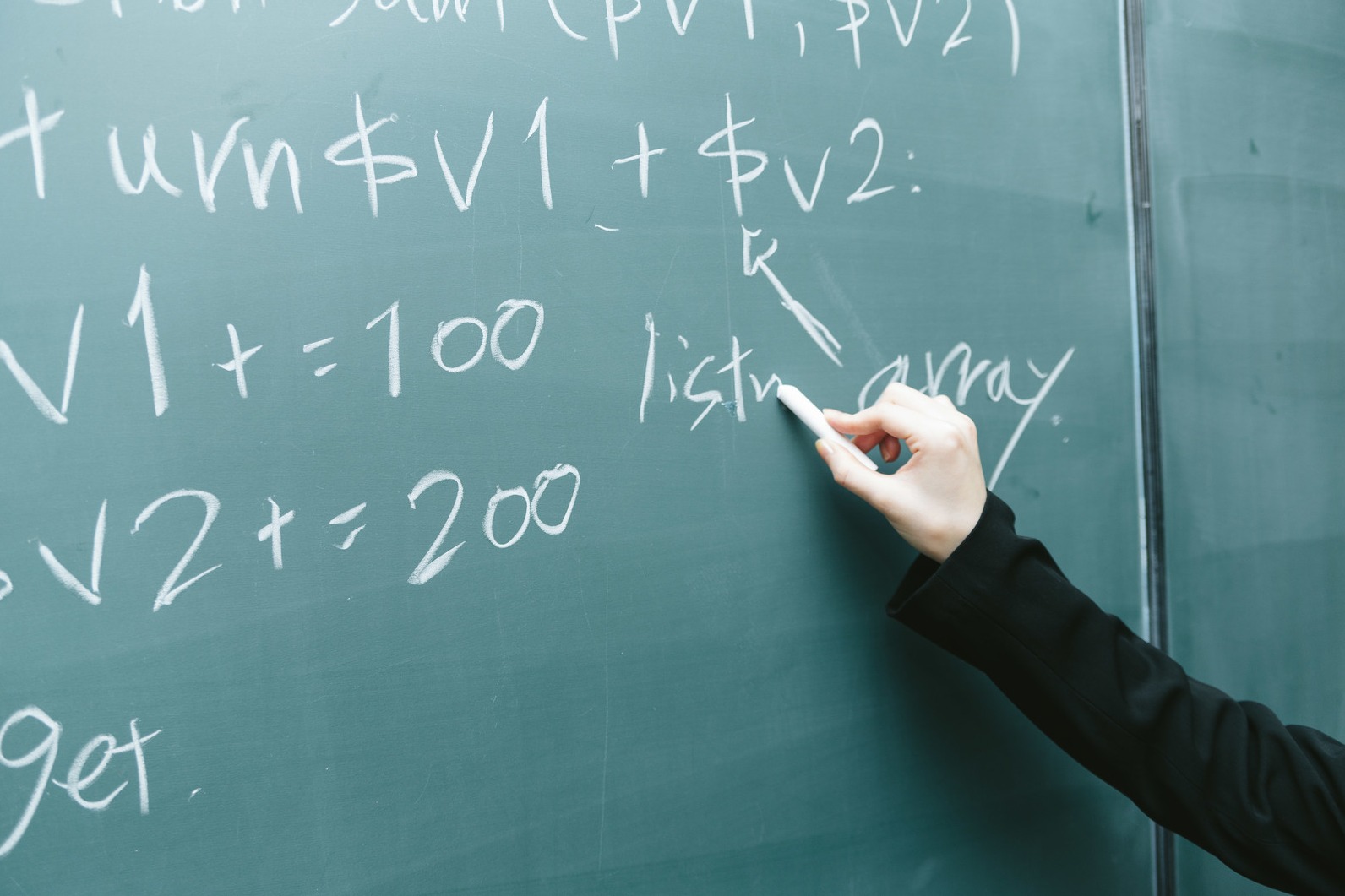
また、フェルミ推定に当たり、覚えておいた方がいい数字についても以前記事を書きましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
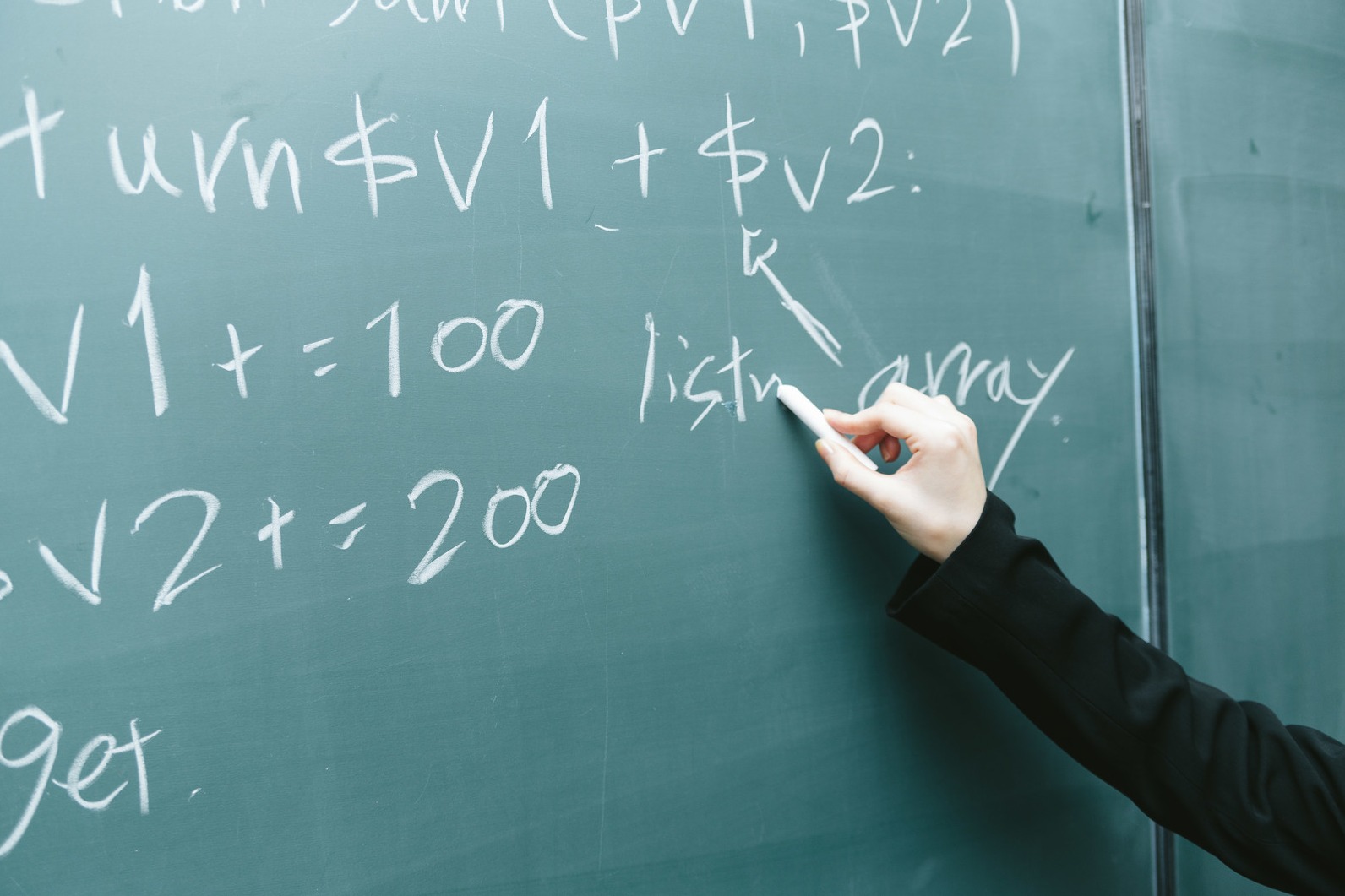
さらに分解&数字置き
では、「年間購入枚数」をさらに分解していきましょう。
企業から年賀状をもらうパターンと、個人どうしの年賀状のやり取りパターンを分けて考えます。
<企業の場合>
年間購入枚数 = 企業から年賀状をもらう人口数 × 平均受取枚数
<個人の場合>
年間購入枚数 = 人口数 × 年賀状の購入者率 × 平均購入枚数
ここで、変数ごとに数字を置けるか考えることになります。
「企業の場合」は、基本的に生命保険会社から送られてくることが大半でしょうから、
- 企業から年賀状をもらう人口数:
社会人の多くが生命保険を契約してるでしょうから、5500万人(= 7000万人 × 80%) - 平均受取枚数:
加入している生命保険は基本的に1社でしょうから、1枚
という感じかと思います。
一方、「個人の場合」に関しては、
- 学生か
- 社会人か
- シニアか
という属性によって数字が変わってくると思いますので、
年間購入枚数 = 人口数 × 年賀状の購入者率 × 平均購入枚数
という式の変数ごとに、属性を切り分けて検討していきましょう。
まず、「人口数」ですが、
- 学生:2000万人
- 社会人:7000万人
- シニア:3000万人
という感じでしょう。
次に、「年賀状の購入者率」ですが、ここの数字は非常に難しいです。
起点にできるほかの数字も思いつかないので、自分の周りの人をイメージして設定するしかなさそうですね。
なので、自分の周りをイメージすると、
- 学生:
年賀状というやり取りに一定の憧れを持っている人もいますが、基本的にはLINEやSNSで年始の挨拶をするでしょう。
30人クラスで2,3人くらいは年賀状を書いているのではないでしょうか。
なので、10%とします。 - シニア:
先にシニアを考えます。
この世代の人たちは、年賀状文化が残っている人たちでしょう。
ほぼ全員がやっていると考え、90%とします。 - 社会人:
最後に社会人です。
LINE等での挨拶も引き続きメジャーですが、社会人になると、仕事関係や親戚関係で年賀状を出す人も増えてくるでしょう。
とはいえ、そういったやり取りをするのはある程度年配になってからだと思います。
実際私もそこまで多くのやり取りをしているわけではないので。
とはいえ、全く年賀状をやっていない人よりは、年賀状をしている人の方が多いと思います。
学生とシニアの間をとって、60%としましょう。
という感じでしょう。
さらに、「平均購入枚数」ですが、
- 学生:
やり取りするとしても友人間くらいでしょうし、4,5枚くらいじゃないでしょうか。
なので、5枚と設定します。 - シニア:
先にシニアを考えます。
うちの祖父母の年賀状を考えると、毎年ハードカバーの本並みの厚さになってます。
80-100枚くらいでしょうか。
ただ、うちの祖父母は田舎の兼業農家なので、親戚の結びつきも強いでしょうし、仕事の関係者も多いと思います。
一般的な家庭はもっと少ないでしょう。
50-60枚くらいという感じでしょう。
なので、50枚と設定します。 - 社会人:
最後に社会人です。
シニア並みに年賀状を出しているとは思えないので、50枚は切るでしょう。
この世代だと、年賀状を出すのは仕事の関係者宛てで、親戚関係ならLINEとかでやってしまう人も多いと思います。
なので、シニアの半分くらいと考え、20-25枚くらいじゃないでしょうか。
したがって、20枚とします。
計算すると?
上記の計算式をまとめて計算すると、
- 企業の市場規模:28億円
- 学生の市場規模:5億円
- 社会人の市場規模:420億円
- シニアの市場規模:600億円
- 年賀状の市場規模(合計):だいたい1100億円
となりました。
計算前には、
三桁億円くらいだろうな
と思っていたので、イメージよりちょっと大きい数字が算出された印象です。
しかし、調べたところ、
- 2021(令和3)年の年賀葉書の総発行枚数:
21億枚くらい - 年賀はがきの値段:
1枚63円
のようなので、市場規模は1300億円くらいみたいですね。
計算のテクニックについては、以前記事を書きましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

オススメの書籍
今回の記事に関連したオススメの書籍は以下の通りです。
『フェルミ推定の技術』
おわりに
いかがでしたでしょうか?
お仕事の参考になれば幸いです!
ケース問題にも取り組んでいるので、こちらもぜひご覧ください!









